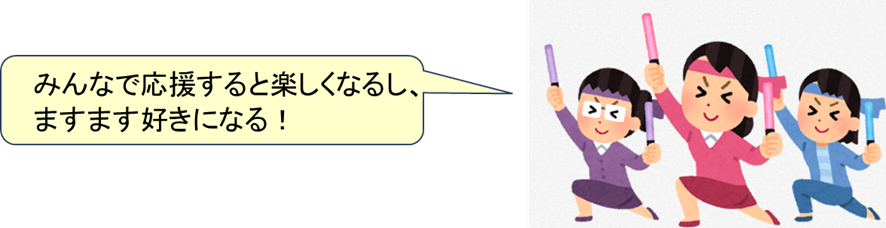新たな消費のドライバー「推し活心理」
「推し活」が拡大している。推しの対象は、SNSをフォローする軽いものから、アイドル、俳優、Vtuber、キャラクター、スポーツ選手、そして大好きな商品やサービスなど幅広い。そして推しへの思いの強さにより、熱烈なファンになったり、また商品を大好きになるなど消費行動に大きな影響を与える。
推し活が広がっている背景には、実質所得が伸び悩み生活が苦しくなる中でも、好きなアイドルや商品・サービスに囲まれていると、ささやかな喜びや小さなワクワク感が得られるからだ。またSNSや動画共有サイトなどのコミュニケーションアプリの進化で、推しが身近に感じられるようになって自分ゴト化できることも大きい。
推し活の消費者心理は、日常生活にメリハリをつけ、また新たな消費行動に駆り立てるきっかけにもなっており、新たな消費ドライバーとして注目される。
推し活で新たな需要創造
JR東海高島屋では、毎年、大規模なバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」(‘01年~)を行っている。’24年は、140のブランドと2600種のチョコレートが品揃えされ、来場者は80万人、売上高は41億円を超える。しかも購入金額が10万円を超える顧客も多くなっている。特徴は、推しの超人気チョコレートシェフが売り場に立ち、ファンの質問に答えたり、一緒に写真撮影をしたり、サインなどのサービスを行う。ファンにとっては嬉しい貴重な体験だ。そして推しのシェフが作った素敵なショコラを家族や友人、そして自分へのご褒美として購入している。シェフにとっては、ファンとの交流を通じて自社商品に対する意見が聴けたり、顧客の特性を把握できることの意味は大きい。今年は目玉としてコアなファンを感動させるために、JR東海とタイアップして新幹線車両2両を貸し切り、推しの人気シェフ5人が参加してトークショーや先行試食会などを行うイベント「ショコラトレイン」を開催した。参加費4.7万円にも関わらず、大好きなシェフと会えるため応募者は150名に及び、抽選で100名が参加した。この催事の様子は、多くのマスメディアの報道やSNSの拡散で大きなPR効果が得られた。
これまでのバレンタイン需要は、「義理」が殆どで「本命」が一部という状況で需要が頭打ちになり、また少子化の影響でチョコレート市場は縮小傾向にある。しかしこの「推しのシェフからの購入」、そして「自分を押しとするご褒美」は、コアなファンからの口コミ拡散効果で新たな需要創造につなげている。
推し活は新しい広告スタイルも創り出している。熱烈なファンが、協働して「推しを応援する広告」を出すことだ。例えば、韓国BTSの誕生日を祝うため、ファンが協力して駅などにセンイル(誕生日)広告を出稿している。アイドルもその広告を見に行き、その様子をネット上に投稿する。ファンにとっては嬉しいリアクションだ。制作費や媒体費は、ファンがネット上で集めて支払うという仕組み。自分達の大好きなアイドルが通行人の目に触れたり、人気を向上させたりする応援活動が楽しく、これがファン心理だ。最近では、イベント情報やファン相互の交流など行うための便利なアプリも充実しているのでこの動きは拡大している。但し、肖像権や著作権の対応が難しいところがあり、推しに迷惑を掛けないためのルールづくりは必要だ。
推しをプロモーションの切り口として活用している事例は多い。S&Bは、「まぜるだけのスパゲッティソース」のプロモーションとして若者層に人気のグループINIを起用し、「キミの推しスパは!?」キャンペーンを行った(’22年)。これは「生風味たらこ」「ツナしょうゆ風味」「イタリアの恵み」など幅広い商品ラインアップを訴求するために11人のメンバーが「推しスパ」を紹介する。そしてXの「#キミの推しスパは」をリツイートすると抽選でオリジナルグッズがもらえるという内容だ。このような推しへの熱量を活用するキャンペーンは、様々な企業でも行われている。
推し活は自分アイデンティティ作り
現代社会は、個人主義の浸透で孤立化が広がっているが、人間は人や共同体とのつながりを求める傾向がある。このような状況の中で推しを持つことは、推しとの心理的な絆が生まれ孤独感からささやかながら解放される。またファン同士で推しを応援することで一緒に喜び合う共体験も得られる。さらに大好きな推しを自分と重ね合わせることで、自分らしさを再認識して自分のアイデンティティを形成することにもつながる。これは単なる趣味の領域を超えて、推し活は楽しさや嬉しさとなり、ある意味、推し活は自分がイキイキとした人生を送るための自己投資にもなる。
例えば、熱烈なファンが多いK-POPアイドルのインタビューやSNS投稿を理解するために韓国語の勉強を始めたり、韓国旅行などの行動を誘発する。さらに推しを応援してブレイクさせることができれば、自分の成功体感にもつながる。
推しを持つことは、感情などがポジティブなエネルギーになり、人生を楽しもうというウエルビーングな生き方にもなる。そして時間やお金の使い方も能動的になり、消費活動も前向になるのだ。
「つながり」が推し活を拡散する
マスマーケティング時代は、「機能性」「皆が使っている」「手ごろな価格」で購入されていた。しかしSNS時代は、機能性は当たり前で、「自分に合う」「好き嫌い」「共感する」という理由で購入されることが多い。推し活は、これらに加えて「つながり」が大きな要素になっている。但し、自分が主体的に参加できる「ゆるいつながり」だ。
そのためには商品に対する共感度の高い人が参加しやすいリアルとネットのブランドコミュニティをつくる。そこでは商品の開発ストーリーやユーザーの感想、そしてファンを一人ぼっちにさせないためのAI解析コンテンツを充実させる。またファン同士のゆるいつながりを促進するコミュニケーションアプリも実装する。そしてコアファンを炙り出し、コミュニティ内での情報発信を促す。コアファンの商品体験は、説得力があり共感が得られやすい。さらにみんなと一緒に推す共体験は商品とのより深い絆をつくる。これを繰り返すことで推しの商品の自分ゴト化を促し、ロイヤルティ向上が図られるのだ。
2025/3/25
縄文コミュニケーション株式会社
モモズプラネット顧問 福田博